全圃場に対応した多機能型自動給水機のシリーズ開発
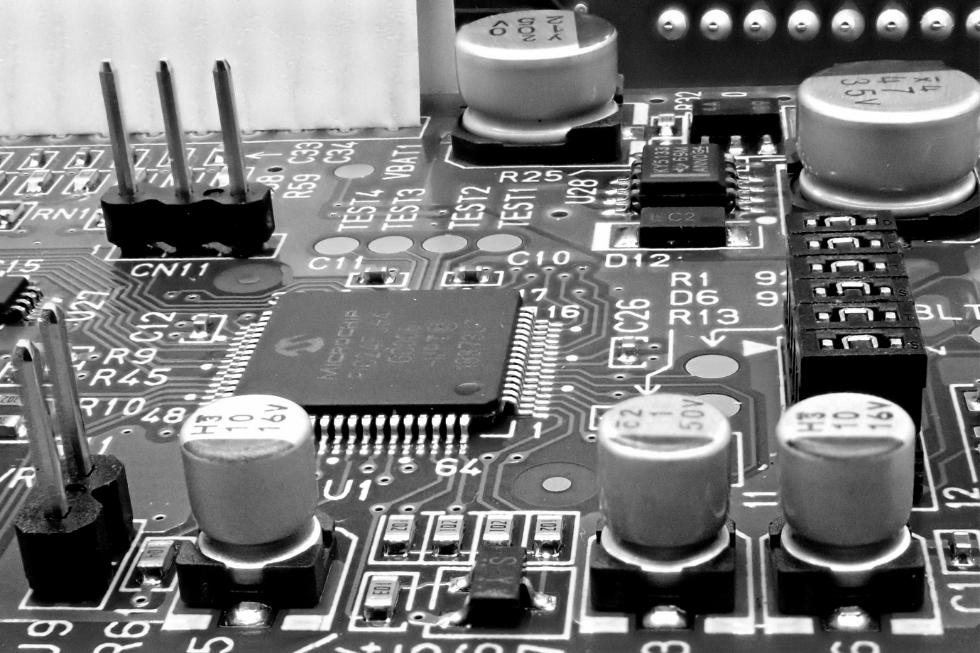
1. 農業の未来に向けた挑戦
日本の人口は減少の一途をたどり少子高齢化が進む中、農業人口の減少は特に顕著で、耕作放棄地は年々増大し、日本の基幹作物である水稲栽培に大きな影響を与えています。特に営農作業の3割を占める水管理労力は、高齢化・人手不足の営農事情には重い負担であり、若年層の農業離れにも繋がっています。
また、昨今の気候変動は米品質や収量にも影響を及ぼしており、収益が減少し、さらなる営農離れにつながっているという側面があります。
日本の農業の現状について述べましたが、もう少し踏み込んで、日本の圃場についてお話します。
日本の圃場の給水方法は、大きく分けて2つに分類できます。一つはオープン水路であり、もう一つはパイプラインです。パイプラインにはポンプ圧送型と自然圧型の2種類があります。現在の気候変動の影響で安定した給水量を確保するため、パイプライン化が推進されていますが、現状では時間と費用が掛かるため思うような整備が進んでいません。
この様な背景を踏まえ、水管理労力を削減し、かつ合理的な水分配により米品質を確保でき、開水路、パイプラインの両方において同じ使い勝手で利用可能な「水まわりくんシリーズ」の開発および市場投入を行いました。
| 大分類 | 要求品質 | 実現方法 |
| 使い勝手 | 給水の手間 | 給水計画により自動給水 |
| どこでも操作可能 | Webによる遠隔操作 | |
| 携帯端末での機側操作 | ||
| 操作パネルによる機側操作 | ||
| コメ品質向上 | 水位・水温による自動給水 | |
| 夜間灌漑(24時間給水対応) | ||
| 施工性 | 冬場の取外し平易化 | ねじ一つで取り外し可能 |
| 盗難防止 | 取り付け部の施錠 | |
| 保守性 | 電源不要 | ソーラー発電および蓄電池 |
| 低ランニングコスト | 1システムで120台制御可能 |
2. 全圃場に対応したシリーズ構成
水まわりくんシリーズは、圧送パイプライン用、自然圧パイプライン用、開水路用の3機種を持つことで、すべての整備圃場に対応可能なラインナップとしました。また、各機種の施工方法、使い勝手を同一とするための回転軸の接続方法の統一、開度の調整、モータートルクの適正化などの工夫をしました。使用するバルブは積水化学工業株式会社製のエアダスバルブ(圧送パイプライン用)及び低圧用水バルブ(自然圧パイプライン用)限定とすることで、総合的なメンテナンス性の向上に配慮しました。
ICTを活用した遠隔型においては、独自LoRa無線を採用することで見通し2kmの範囲に加えて機器間のマルチホップも可能な方式とすることで最大6kmの運用が可能なシステム構成としました。3つのシリーズはそれぞれに機側設定型と遠隔設定型のタイプを用意することで、色々なユーザー属性にも配慮したシリーズとしました。

3. 大幅な労働力削減
水まわりくんシリーズの導入効果としては、水管理の省力化に加え作物の品質向上が期待できます。加えて用水の効率的な利用や、無駄なかけ流し防止による環境保全効果も期待できます。
採用例として、種もみ水田の実績をご紹介します。
富山県の種もみは、北は東北から南は九州まで43都府県に出荷され、生産量は日本一を誇っています。種もみの生産は、通常の食用米以上に品質管理が重要で、こまめな水管理や異茎抜き作業、病害虫防除などきめ細やかな作業を経て圃場審査基準をクリアする必要があります。中でも水管理は米品質を確保する重要な作業となっています。
農事組合法人古上野シードファームでは、高齢化によるリタイア発生などが原因の労働力不足を補うため、農地の集積やICTの導入を推進してきました。令和元年から2年間、水まわりくんをテスト導入し評価した結果、水管理工数が約7割削減できたという結果が得られました。このことを踏まえ、同ファームでは、令和3年にパイプライン圃場用に100基及び開水路圃場用に8基の水まわりゲートくんを導入し、11名の営農者によりPCまたはスマートフォンを利用した水管理を始めました。
同ファーム作成の工数比較表が示すように令和元年の導入結果では、手動で水管理を行った圃場と比較して見回りを含む水管理工数は1,502時間から445時間まで削減されたという結果になっています。給水および止水の管理工数だけをとってみると1,151時間から159時間へと大幅に削減しました。| 単位:時間 | 自動給水栓区 | 手動 | ||
| 給水および止水管理 | 巡回および画面管理 | 給水および止水管理 | 巡回 | |
| 5月 | 15 | 75 | 384 | 8 |
| 6月 | 46 | 79 | 333 | 68 |
| 7月 | 52 | 51 | 239 | 145 |
| 8月 | 46 | 81 | 195 | 130 |
| 小計 | 159 | 286 | 1,151 | 351 |
| 総合計 | 445 | 1,502 | ||
4. 進化し続けるブラッシュアップ活動
日本の農業を維持・発展するには、働き方改革を推進し、若い労働力をいかに確保するかが鍵となります。そのための重要な要素として、質の高い収穫による安定収入、ICTを活用した作業の平準化・標準化、タイマー機能やWeb利用で離れた場所からの操作による余剰時間・休日の確保などが挙げられます。
弊社では、さらなる効率化を目指し、既存の水位センサーおよび水位水温センサーについて、クラウドを経由せず無線化できるユニットの開発を行っています。これは、水まわりくんの独自機能であるスタンドアロン機能とホップ機能に組み合わせることで、中山間地域等の通信環境が整っていない地域でも、安定的かつ容易に水管理を行うことができるものです。この無線化できるユニットの開発は令和7年2月27日付で農林水産省より開発供給実施計画の認定を頂きました。
また、連携や共創においても、農業関連の各メーカーや通信事業者との普及活動・システム連携などを積極的に行っております。研究開発分野では東京大学との共同研究など水稲栽培における水管理手法について探求を進めております。
水まわりくんシリーズが時代に合わせて常にその一助となるよう今後も改善・改良を加えていきたいと考えています。
